この話は、今回の話題『死神の肖像』に、読者が「正月早々縁起でもない」とアレルギーを起こさないよう、編集者として気を遣っているのだと思し召しください。編集:高橋 経
--------------------------------------------------------
死神の肖像、いろいろ
ヒラリー・イルケイ(Hilary Ilkay)
ラファムの季刊(Lapham's Quarterly)2014年1月4日号から抜粋
イングマー・バーグマン(Ingmar Bargman)創作、1957年の映画『第七の印章(直訳 The Seventh Seal)』に、黒い頭巾で蒼白、無表情な顔面を包み、身には風にはためく黒衣をまとった死神が登場する。その不気味な容姿に出逢い、「お前は何者だ?」と詰問する騎士アントニアス・ブロック(Antonius Block)の運命に、観客は一様に『死』の暗示を予感する。二人の間で、『死』に僅かな執行猶予期間を与える合意が成立するのだが、その経緯の描写は知的で実存主義的、ウイットがあり騎士の心中に起こった動揺を微妙に表現していた。
バーグマンは、この場面を形成するに当たり、アルベルタス・ピクター(Albertus Pictor)が15世紀に描いた壁画からインスピレーションを受けていた。スエーデンのタビィ教会(Taby Church)に遺っているその壁画は、一人の男が骸骨の死神とチェスの対決をしている情景を描いたものである。
古代社会では、『死』は、しばしば黄泉の国(よみのくに:つまり、あの世)を司る帝王という形で擬人化されていた。エジプトの神オシリス(Osiris)は皇帝の神聖な範例で、死後また復活すると信じられていた。この場合、オシリスは『死神』であった。(ミイラ、その他の叙述は省略)
他の文明社会では、伝統的に女性が『死神』を象徴していた。中世ヨーロッパで蔓延した黒死病その他の病厄は、何百万人という人命を奪った。この絵は、1890年頃、エヴェリン・ド・モルガン(Evelyn de Morgan)描く『死の天使(The Angel of Death)』。(14世紀フランスのフレスコの記事省略)
セオドール・セヴェリン・キッテルセン(Theodor Severin Kittelsen)描く『ペスタ、1(Pesta 1)』1904年頃。キッテルセンは、スカンジナビアにおける疫病の擬人化を試みている。ペスタとは、疫病と死を象徴する醜い腰の曲った老婆である。
19世紀から20世紀の初頭にかけて、過去の習慣から引き続き画家達は『死神』を女性で象徴させてきた。このベルギーの版画家、フェリシアン・ロプス(Félicien Rops)描く『人間パロディ(The Human Parody):1878年頃』では、束の間の女性美の表面を捉えている。近づく男性の欲情をそそる魅惑的な女性は、美貌の仮面の裏側に骸骨を潜ませている。これこそ人間性のパロディで、我々の煩悩を露呈する外面というワナを象徴している。
その20年余り後、1901年から1902年にかけて、画家で文筆家のアルフレッド・クバン(Alfred Kubin)が、ペン画で『死神』の正体を暴こうと試みている。この『最良の医者(The Best Doctor)』と題した作品では、気味の悪い性別不明、長髪、筋骨質の腕が伸び、平たい胸のくせに黒衣の曲線は女性的な体型を誇張している。こうした容姿は『薬』を象徴し、薬の力に頼ることによって救われると思い込ませ『最良の医者』ではなかった『死神』が、瀕死の患者の目を閉ざすと同時に、顔を圧迫し、窒息死に陥しいれてしまう。
それと対照的に、カルロス・シュワブ(Carlos Scwabe)が描いた『墓堀り人夫の死(Death of the Gravedigger):1895年頃』に描かれた死の天使は、神秘的で優雅な容姿の内にダイナミックな女神像の尊厳さを持たせ、弧を描く翼は、自身と墓堀り人夫とを共に包容する。こうして、死につつある人夫に、平穏な最期の素晴らしい夢を抱かせているのである。
異論はあるだろうが、古今を通じて骸骨は『死神』の最も一般的な象徴として認められてきた。ハンス・ホルバイン(Hans Holbein)の「死神の踊り(The Dance of Death)」の連作から『貴婦人(The Noble Lady):1532年頃』。この木版画は、その代表的な作品の一つであろう。「踊り」は多分に教訓的な意味合いをもっている。つまり、男女貴賎の如何を問わず、『死』は誰もが避けられない運命にある。
その他、死に関してよく取り上げられる話題に、『処女の死(Death of the Maiden)』とか、それに関連した『死神の接吻(Kiss of Death)』がある。この絵は前者の、ハンス・ボルダング(Hans Baldung)作の『処女の死:1517年』である。この作品では、血色の悪い(当然のことながら)屍体が処女の背後に絡み付き、豊満な肌に流れる髪の毛を掴んでたくし上げ、顔を向ければ、骨張った唇とキスをする羽目になり兼ねない瞬間を描いている。(エドワード・ムンチ:Edward Munchの作例は省略)
典型的な『死神』の肖像は、骸骨が黒衣をまとい、頭巾の奥深く「サレコウベの顔」は殆ど見えない。孤を描く長い刃のある草刈り鎌を持っているのが特長であるが、この作例では敢えて見せていない。
装飾的な画風で知られるガスタフ・クリムト(Gustav Klimt)が描いた『死と生(Death and Life: 1910年)』では、『死神』が草刈り鎌を構えて、「生」を象徴する一塊の人々を、いつ何時(なんどき)でも「刈りとる」体勢にある。あたかも、ヨーロッパ中にコレラが蔓延していた時代であった。
典型的な『死神』の草刈り鎌のイメージは、西欧諸国では依然として受け継がれ、落書きにも見られる。1850年代に流行したロンドンの風刺マンガに刺激され、落書きで悪名を流したバンクシー(Banksy)と名乗る「町の絵描き」は、イギリスのブリストル港(Bristol)に停泊していた船の側壁に、スプレー缶絵の具で「草刈り鎌を持った死神」を描いた。強いて題名を付けるなら『モノ言わぬ警備員(The Silent Highwayman)』としておく。不正な社会現象を「刈り取る」べく、バンクシーができた抗議行動の一端であろうか。
(この論説の締めくくりに、筆者はバーグマンの創作上の思想を書いているが省略)









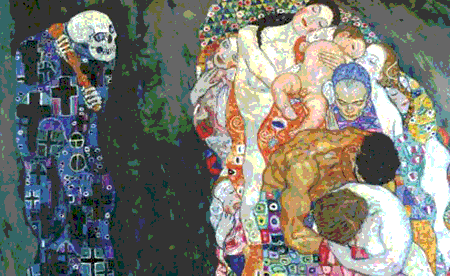

死は避けられないと知りつつも、死の準備をするのは億劫です。でもいつかはしなければなりますまい。
返信削除