志知 均 ( しち ひとし)
2013年7月
 |
| 月岡芳年の妖怪画連作より鷺娘 |
しばらく前にテレビ・ジャパンの番組『日本芸能百花繚乱』で名古屋踊りの『鷺娘(さぎむすめ)』をやっていた。私の祖母も母も名古屋生まれで西川流の名古屋踊りを習っていたから、この踊りについてはよく耳にした。そんなわけでこの番組は懐かしかった。とくに二人の娘が傘を広げて左右対称に近付いたり離れたりする所作は美しい。
左右対称(symmetry)は名古屋城の天守閣を飾る金の鯱(しゃち)のように建築美とされてきた。いや建築だけでなく、芸術一般に美の基準として取り入れられている。これは古代に発達した幾何学と関係があるようだ。歴史的考察はともかくとして、左右対称は自然界、とくに生物には無数にみられる。蝶、花、鳥、ヒトの体、、、。ヒトの体では特に鼻筋の右と左が均整のとれた顔であり、全身でも左右均衡であることが美の条件として要求される。
しかし、「美貌はただ皮一重(Beauty is but skin deep.)」といわれるように、体の内部にある臓器(ぞうき)はその形も配置も左右対称とは程遠い。例えば、手の甲に透いて見える静脈をとっても、右手と左手では全然違う。
 ヒトの体の外観は大体左右対称だが、手足の動きはそうではない。左利きに比べて右利きが圧倒的に多い。野球のピッチャーは右利きが多いし、ほとんどのフットボールの選手は右足でキックする。余談だが左利きは英語でleft-handednessとかsinistralityと言うが、あまりよい意味では使われない。Sinistrality の語源は不幸をもたらすものという意味の sinisterにあるし、left-handed marriageと言えば、古い時代に身分違いの結婚や正式に式をあげない結婚を意味した。これらはあきらかに少数派の左利きへの偏見に基(もと)づいている。
ヒトの体の外観は大体左右対称だが、手足の動きはそうではない。左利きに比べて右利きが圧倒的に多い。野球のピッチャーは右利きが多いし、ほとんどのフットボールの選手は右足でキックする。余談だが左利きは英語でleft-handednessとかsinistralityと言うが、あまりよい意味では使われない。Sinistrality の語源は不幸をもたらすものという意味の sinisterにあるし、left-handed marriageと言えば、古い時代に身分違いの結婚や正式に式をあげない結婚を意味した。これらはあきらかに少数派の左利きへの偏見に基(もと)づいている。 興味あることに右、左の体の使い分けはヒトに限らず下等動物でも見られる。生物学者の観察によれば、それは自己保存(生存)のための状況によって決まる。体力補給に不可欠である餌あさりでは、魚、ヘビ、トカゲ、カメなどすべて右側にある餌を右眼でよく見て捕らえることが多いという。動物園でサルやチンパンジーにバナナを投げ与えると、殆どの場合右手で受け取る。餌をあさるのとは反対に自己防衛の場合には、自分の生存を脅かすものが視野の左側にくるのを避ける生物が多い。それと関係して、発情期に同類と闘う時はカメもニワトリもサルも相手の弱点である左側を攻めることが多いようだ。私も子供の頃剣道を習ったとき、正眼の構えでは左方への動きが右方への動きより多かったのを思い出す。拳闘(ボクシング:上図)でも即座の防衛は左手でする。
興味あることに右、左の体の使い分けはヒトに限らず下等動物でも見られる。生物学者の観察によれば、それは自己保存(生存)のための状況によって決まる。体力補給に不可欠である餌あさりでは、魚、ヘビ、トカゲ、カメなどすべて右側にある餌を右眼でよく見て捕らえることが多いという。動物園でサルやチンパンジーにバナナを投げ与えると、殆どの場合右手で受け取る。餌をあさるのとは反対に自己防衛の場合には、自分の生存を脅かすものが視野の左側にくるのを避ける生物が多い。それと関係して、発情期に同類と闘う時はカメもニワトリもサルも相手の弱点である左側を攻めることが多いようだ。私も子供の頃剣道を習ったとき、正眼の構えでは左方への動きが右方への動きより多かったのを思い出す。拳闘(ボクシング:上図)でも即座の防衛は左手でする。 |
| 脳を上から見た左右半球 |
言葉も音楽も耳から入ってくる音だが、その両方を認識しようとすると脳の両側が同時に活性化するので混乱することがある。楽器の演奏や読書に夢中になっている人に話しかけても耳に入らないのは、活性化している側の脳が話しかけられた声(雑音)を拒否するからである。しかし何かに注意を集中している場合を除いて、日常生活では脳の右も左も程度の違いはあれ、同時に働いている。
 脳が全体として働く時は左半球と右半球にある神経細胞の間で情報交換が密接に行なわれる。それがうまくいかないと行動に異常をもたらす。脳は複雑な電気回路でできたコンピューターのようなもので、それを構成するのは神経細胞のネットワークである。ネットワークの基礎は生まれてから3歳ぐらいの間につくられる。三つ子の魂百まで、とはよくいったものだ。ちなみに、右利き左利きの違いは、胎児か新生児の段階で脳の神経ネットワークの形成にわずかな違いが起きたのが原因なのであろう。それに対し、年々数が増えて社会問題になってきている自閉症の子供達では脳神経ネットワークの形成に深刻な異変があったのだろうといわれる。幸い幼児の脳は柔軟性(plasticity)があるので、3歳過ぎてからでも、例えば言葉の訓練で左脳のネットワークを修復すれば言語障害が直ってくるように、自閉症の症状を訓練である程度改善することができる。
脳が全体として働く時は左半球と右半球にある神経細胞の間で情報交換が密接に行なわれる。それがうまくいかないと行動に異常をもたらす。脳は複雑な電気回路でできたコンピューターのようなもので、それを構成するのは神経細胞のネットワークである。ネットワークの基礎は生まれてから3歳ぐらいの間につくられる。三つ子の魂百まで、とはよくいったものだ。ちなみに、右利き左利きの違いは、胎児か新生児の段階で脳の神経ネットワークの形成にわずかな違いが起きたのが原因なのであろう。それに対し、年々数が増えて社会問題になってきている自閉症の子供達では脳神経ネットワークの形成に深刻な異変があったのだろうといわれる。幸い幼児の脳は柔軟性(plasticity)があるので、3歳過ぎてからでも、例えば言葉の訓練で左脳のネットワークを修復すれば言語障害が直ってくるように、自閉症の症状を訓練である程度改善することができる。 |
| 鞭毛(cilium) |
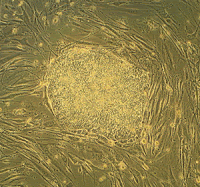 |
| 胚子(embryo) |
それが胎児、新生児の頭脳機能の左右の違いにどう結びつくかの解明は今後の課題だが、このような胚子の段階での左右の違いは脊椎動物が現れた5億年前まで遡(さかのぼ)るようだ。脳の左右の違いは長い進化を経てできてきたわけである。
左右に関しては、まだ色々面白い話題があるはずです。お気が付きましたらご投稿ください。
返信削除